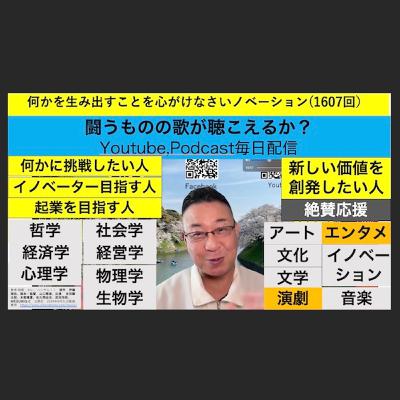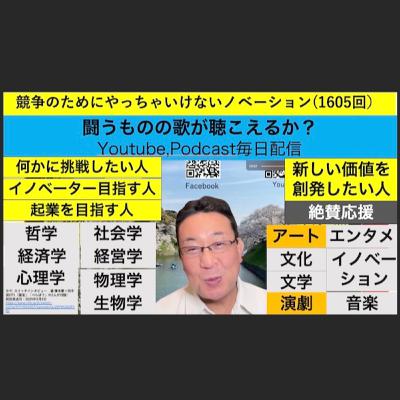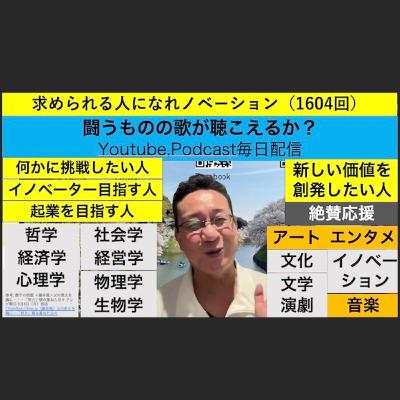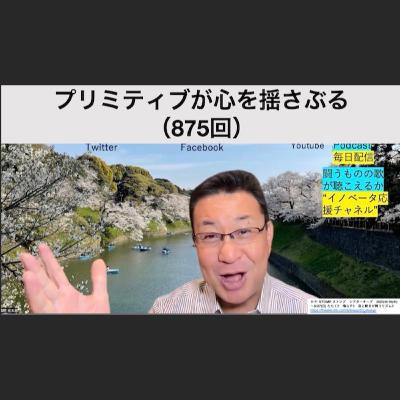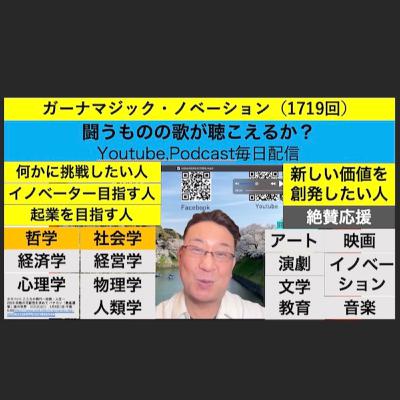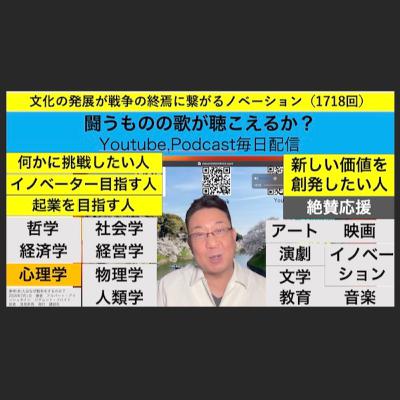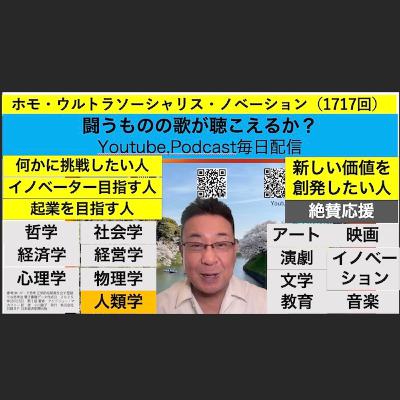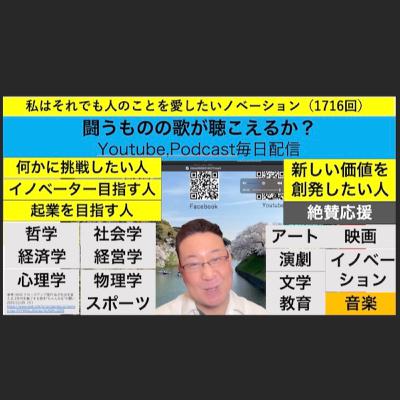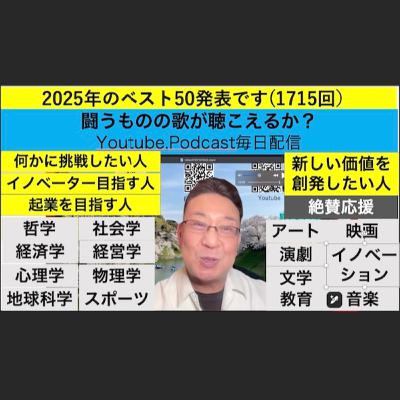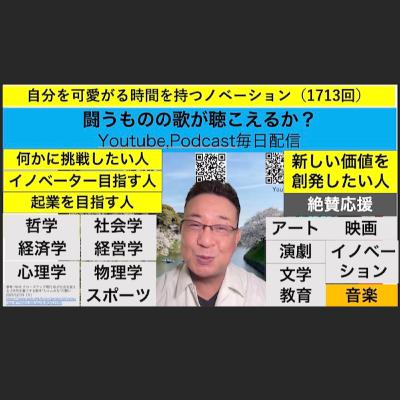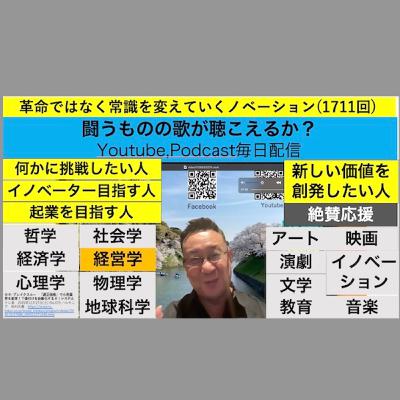Discover 残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"
残間光太郎の"闘うものの歌が聞こえるか"

1729 Episodes
Reverse
映画"おいハンサム!!"のお父さん(吉田鋼太郎)さんの言葉に、痺れました曰く"お前たちは。今のところ平和な国に生まれ育った。美味しいものを食べていい服を着て楽しく暮らしことは簡単だろう。でも。ただ、消費して。それを疑問に思わない人間にはなるな。消費することが幸せなら、たくさんお金を使える人が、たくさんお金を持っている人が一番幸せということになる。そうではなくて。なんでもいい。何かを生み出すことを心がけなさい。どんなに平凡な仕事だって、掃除だって、料理だって、ゴミの分別だって困っている人を助けること、悲しんでいる人を力づけること、迷っている人に寄り添うこと。転んでしまった人を見捨てないこと、みんな立派な生産だ。立派な創造だ。だから、これから各自どう生きるのか立ち止まって、ゆっくり考えなさい。一日一日を精一杯生きられなくたていい。普通に生き続けなさい。明日からもお前たちの人生は続くんだから。そうだ、それが重要。生き続けなさい。"ここから私は思いました1、消費と創造2、誰もが創造者3、立ち止まって考えること1、消費と創造このドラマは大好きで、シーズン1からシーズン2、そして映画までを、一気に見返してしまいました!吉田鋼太郎さんという、少しウザがられながらも毎回ハンサムな言葉を言おうとする家族を愛する親父と、マイペースな母(MEGUMIさん)、個性あふれる三姉妹(木南晴夏さん、佐久間由衣さん、武田玲奈さん)の毎回コメディだけれども、とても深く考えさせられるテーマに、釘付けでしたその中で、今回の映画のラストシーンの言葉は、原作の伊藤理佐さん、脚本・監督の山口雅俊さんのパッションが炸裂する、感動の涙なしでは見られないハンサムな言葉でした消費と創造、という世の中を二項対立で表現するのは、複雑な世の中をわかりやすく表現するのにとても便利なやり方だと思いました。太刀川さんの進化思考における、変異と適応、または、オライリーさんの両利きの経営における、探索と深堀、のように、内容は違いますが、人の人生において、消費と創造が、くるくる回っているイメージは、確かになあと思いましたとかく、生きるため、贅沢をするための消費の方に目が向かってしまいますが、必ずどこかで創造をする人がいなければならない、そして、自分はどちら側にいるんだろうという問いを、持つことにとても重要な意味がある気がしました2、誰もが創造者このお父さんのお話を聞いて、まず思い出したのが、ハーバード大学・京都大学名誉教授の広中平祐先生の「創造のある人生こそ最高の人生である」という言葉です結婚をすることだって、庭の手入れをすることだって、編み物をすることだって、実は全て、創造的な活動であるということです。それが、誰かの痛みや顔を思い浮かべながらやることこそが、イノベーションの種に繋がり、自分一人で出来なくなったら、仲間と共に、みんなが喜んでくれる大義を実現する、パッション、仲間、大義と広がるイノベーターリップルモデルに繋がると思ってますそこから誰かが喜んでくれたり、感謝のループが回り始めると、それはその人の生きがいに繋がっていく誰もが創造者やイノベーターになれるし、それこそが生きがいにつながる道筋の一つだと、そんなことを思いました3、立ち止まって考えることお父さんが最後に言ってくれてますが、それを感じるためには、一度立ち止まって、自分の今を見つめてみるということと思いましたとかく忙しすぎて、毎日のタスクをこなすだけで精一杯になっちゃって、自分が大好きなこと、誰かのためにしてあげたいこと、個性を発揮したいこと、成長・脱出したいことが、見えなくなってしまう、ということが誰にも起こる、ということかと思いましたこれを私は、自らのパッションの源を見つめ直してみること、と言ってますが、ほんの少しだけでも、それを考えるだけで、変わってくるんじゃないのか、そんなことを改めて思わせてもらいましたと言う事で一言で言えば何かを生み出すことを心がけなさいノベーションそんなことを思いました^ ^参考:映画 おい、ハンサム!! 原作 伊藤理佐、脚本・監督 山口雅俊、出演 吉田鋼太郎、木南晴夏、佐久間由衣、武田玲奈、MEGUMIなど 公開日 2024年6月21日配給 東宝 https://www.oihandsome.com/movie/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/A6lbkgNjbwE
画家の有元利夫さんと、演劇評論家の松岡和子さんとの、対談に、真実への向き合い方を、教えて頂きました曰く"有元さんやっぱ象徴性がないとねいっぱい嘘つかないとさ、真実から遠ざかるって感じがあるじゃない松岡さんいっぱい嘘ついて、いっぱい演技して、ある様式を抽出すれば、それがより真実になるってことよねシェイクスピアの芝居っていうのはものすごく双子がたくさん出てくるのが多いわけそういう場合ね本当の双子を使っちゃったら面白くないわけ有元さん女工さんの役やるから、女工さんのね、衣装借りてきたとかさその汚れた作業着をそのまま舞台で着るなんていうこと自体がね もうすごいナンセンスでリアリティーからどんどん、離れていくっていう感じがするのね松岡さん舞台というところは演技をする空間である。嘘をつく空間である有元さんそれで真実に近づく"ここから私は思いました1、真実はない、あるのは解釈だけ2、具体と抽象の往復運動3、伝えるべき真実をいかに伝えるか1、真実はない、あるのは解釈だけ有元さんの絵画は、とても個性的で、様々なものがシュールに組み合わさっていて、そしてとても静かに止まっているようでいて、それがこれから動き出すのか、どこからか動いてきたのか、静かでありながら音楽が流れてくるようで、こちらの心をうごささざるを得ないような素敵な絵なのですが何故このような絵を描くに至ったのかを、このお二人の対談によって、一つのヒントを頂いたような気がしました真実はない、あるのは解釈だけ、とは、ニーチェの言葉ですが、現実の事象があったとしても、それをどのように見るのか?または、その背景に何があってそうなったのか?という、真実は、実は見る人各々によって変わってくるという話かと思います各人にいろんな真実がある中で、誰かから伝えたい本当の真実と信じるものがあるとすれば、嘘も含めたあらゆる角度からの、アプローチでそれを炙り出させる、または、これまで真実だと思われていたものに楔を刺す、そんな考え方もあるかなと思いました2、具体と抽象の往復運動細谷功さんの、具体と抽象の本が好きなのですが、ある具体的な事象のものを、さらなる抽象化をすることで、そこにある本質的な価値や意味を見出して、そして、さらに別の具体的な事情として表現するということがあるかと思いますイノベーションの世界でも、ある業界における個別のイノベーションがあったとして、それを一旦抽象化してみることによって、提供される価値を抽象的に把握して、そしてそれを具体的な別業界に転用していくということが、イノベーションを横に展開する手法としてありますここで言われている話も、女工さんの個別具体な衣装を持ってくるよりも、もっとそこで伝えたい価値を抽象化した上で、全然違う衣装としてやった方が、伝えたい価値が伝わる、そんなことがあるのかもしれないなあと思いました3、伝えるべき真実をいかに伝えるか舞台やアート、音楽でも、創作物は、ある意味、人間が作り出す新しい物語でよくて、嘘だらけのものだからこそ、真実が炙り出てくる、ということがあるんだなあと思いました例えばアートで、写実的な精巧な写真のような絵画でその時の感動を伝えることもあれば、印象派のように、近づくと何を描いてるのかわからないのに、遠目で見ると、ものすごい光の爆発があって、そこに作者の伝えたい感動があるのかあ、みたいなことがあるよなあと思いましたそれは、ある意味、絵の具という嘘の線で描かれたものだけれども、それがより集まって一つの様式になると、爆発的な伝えたい真実が浮かび上がってくる、そんなことってあるのだなあと思います真実は一つではないし、各人によって全く解釈で違うのだけれども、そこにある抽象的な価値のようなら伝えたい真実は、発信する人からは明確に、自分の中にあって、でもそれを伝えるためには、嘘で表現することを重ねることが1番伝えたいことに近づく、そんな試行錯誤の連続なんだろうなあと思いましたイノベーションの世界でも、そこにどんな価値を提供したいのか、どんな世界を実現したいのか、という大きな真実や大義があって、あらゆる手段を使ってそこに近づこうとする、それが直接的な解決策ではなくても。そんなことが、大切なのかもしれないと思わせていただきましたといえことで、一言で言えばいっぱい嘘をつかないと真実から遠ざかるノベーションそんなことを思いました^ ^ 参考:Eテレ東京 NHK 日曜美術館 だからあんな不思議な絵を~天折の画家・有元利夫と家族~2025/9/14 https://www.nhk.jp/p/nichibi/ts/3PGYQN55NP/episode/te/47N8R8X7W1/動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/KTh_Cyb3S04
ダンサーで俳優の田中泯さんと俳優の橋本愛さんの対談で、田中さんからの言葉に痺れました"一生懸命体を鍛えて、その動きができるようにしていくっていうのも。 1つの方法で、それも踊りの 1つのあり方なです。それを否定する気全くないし。でも、一番大事大切なのは、競争のためにそれをやっちゃいけない。踊りのためにやらなくちゃないそこが一つの番重要なことだと思います。競争をすると、多分自意識がさらに高まってきます。確かに。そうすると見たくない人が、絶対現れてきます。要するに、見る人って動いている人の踊っている人の体の中に入りたくなるんです。なりますよね。そこが踊りなんです。"ここから私は思いました1、内発的動機から動いてるか2、パッションの源を見つめ直す3、大義が仲間を連れてくる1、内発的動機から動いてるか田中泯さんが、フリーダンサーだったということが、衝撃だったのですが、それであの存在感のある演技が生まれてるのかと、勝手に合点が行った気がしました競争のためにやっちゃいけない、との言葉には、田中さんの生き様が反映された言葉なのかと思いました。そこから思うのは、他の人たちがどうであろうと、自分が信じることをやる、という、田中さんの内発的動機から動く姿勢が現れた言葉かと思いましたデシさん&ライアンさんの有名な自己決定理論からですが、報酬や評価、罰などから生じる外発的動機からは、「外的報酬は、一時的に行動を強めるが、内発的な興味を損なう可能性がある。」とのことがあり逆に内発的動機は、「人は自分の行為を自分自身の選択として経験する時、最も強い動機を感じる。」と言われておりイノベーティブな活動は「やらされ感」ではなく「自ら選んだ感覚」からこそ生まれる。自律性を守ることが創造性の持続の鍵。」ということに、とてもシナジーがある考え方だなあと思いました2、パッションの源を見つめ直す内発的動機を持つためにはどうしたら良いかということについては、デシさんとライアンさんは、自立性、有能感、関係性が大切と言われてますが私は自らのパッションの源がわかっていることがとても大切だと思っています。忙しすぎるととかく、やらされ仕事や、また日々生活をするためにやってることに忙殺されますがそこでほんの一瞬でも、みずからのパッションの源ってなんだっけ?という時間を、お風呂の時でも、寝る前でも、考えることが大切と思ってます田中さんは、その自らのパッションの源は、ずっとブレずに、踊る、ということにあったということだと思うと、大好きパッションの炸裂であり、さらにとにかく個性的なその場踊りをするという唯一無二さをみるに、個性派パッションも、同時に炸裂していたのではと、勝手に想像しましたそんな田中さんは、もはや誰と競争をするとは別次元の自らの踊りを追求する、ということにあったのではないかと思いました3、大義が仲間を連れてくる田中さんが俳優の世界に入ったのは、ある映画に誘われたからとのことでしたが、その映画の中でも、踊るシーンではないのに、田中さん踊ってましたね、と言われたそうです田中さんは全くの俳優としては初めての経験だったにも関わらず、絶賛されて、そこから俳優の道が今に続いているということを伺うに田中さんの、踊る、ということにより、人がその人の踊りに入りたくなってくる、という大義が生まれて、その大義は、踊りだけじゃなく、俳優という表現方法にも、同じく、演じてる人に没入していく感覚と同じなのかもしれないなあと思いましたそれを見出した映画監督もすごいし、さらにそれを見事に受けて表現し切った田中さんも凄いなと、思わざるを得ませんでしたイノベーションの世界でも、オープンイノベーションでベンチャーと大企業が共に仕事をする上で大切なのは、目指すべき大義が同じ方向を向いている、ということがあるので、ある意味、オープンイノベーションの一つとして、新しい価値が生まれたのかもしれないなあとも思いましたということで、一言で言えば外敵動機ではなく、内的動機に基づいて競争のためにやっちゃいけないノベーションそれがとても大切と教えてくれているような気がしましたそんな話をしています^ ^参考: スイッチインタビュー 選 橋本愛×田中泯EP1「国宝」「べらぼう」の2人が対談!初回放送日:2025年9月5日https://www.nhk.jp/p/switch-int/ts/K7Y4X59JG7/episode/te/Z2PW2GXRYP/
徹子の部屋での、藤井さんと徹子さんとの会話に、めちゃくちゃ感動してしまいました"徹子さんでも、お父様岡山から出んでもええっておっしゃってたんですって。風さんそうですね。それはでもね、お願いするんじゃなくて、される方になりなさいみたいなね。教えがです。徹子さんで、今そうでしょ。お願いしてくれる人が現れて。みたいなのでしょうね。風さん求められる人になれ。本当に我慢しました。だから僕も。徹子さんあなた自身は、岡山から出られないと思ってらしゃんですって、初めは。だから、本当に求められる人にならなきゃ、ここから。 風さんうん、ここからどこかへはいけないだろうなっと思ってましたね。だから本当に求められる人になろうっていう努力を自宅でしてたし。 まあ、時代もあって、自宅からいろんなものが配信できる時代でもあったのでそうですよね。そう、できることしようってなりました。"ここから私は思いました1、脱出・成長パッション2、受け入れる素直さ・信頼・愛3、やり切る力1、脱出・成長パッションあれよあれよという間に、世界的アーティストになった藤井風さんの、素敵な性格と価値観が伝わってくる、本当に素敵な対談でした私はいつも、情熱のポートフォリオというのがあって、縦軸に、ポジティブネガティヴ、横軸にオープンクローズをとると、大好きパッション、利他パッション、個性派パッション、脱出成長パッションというのが、誰にでもあるパッションとして整理しやすいよという話をしていますが今回の風さんの話は、まさに、脱出成長パッションに、お父様が火をつけてくれた、ということなのかもしれないなあと思いました脱出成長パッションは、世界的なイノベーターの、例えばスティーブ・ジョブズさんや、イーロンマスクさんなどのような方々が、幼少期の経験から、そこから抜け出して、更なる成長をしたいという感情やコンプレックスが、将来すごい花を咲かせるということに繋がる、非常に強いパッションとなる可能性を秘めているのでまさに、お父様がその火付け役となり、それに風さんが答えた、ということの結果として、今の風さんに繋がってるのかもしれないと感動しました2、受け入れる素直さ・信頼・愛風さんのお話を聞いていると、とてもお父ちゃんとおかあちゃんが好きで、強い信頼関係と、もっと言えば、愛し愛されてるんだなあと思いましたここから出さない、なんて言われたら、ぐれてしまってもいいようなところを、素直に実直にその教えを守り抜いて貫いていくことができたのは、そのためではないかと思いましたWBCで栗山監督が、黒板に、できるやつはやるな、書かれたという、信頼してるぞ、というメッセージが、大谷さんと村上さんを大活躍させたように家族の信頼関係が、すべての基盤にあるからこそ、今の風さんがおられるのかなあと、思いましたBCGの秘伝のタレにも、素直である心、というのがあって、ビジネスにも実はそれは、繋がるよなあと思いました3、やり切る力求められる人になるために努力し続けました、というのはいうのは簡単ですが、並大抵のことではないよなあとも思いました成功したベンチャー企業の方に、何故成功したと思いますか?と聞いた際に、必ず言われるのが、諦めなかったらです、という答えです何故、諦めずに進むことができたのかは、私は、それが、自らのパッションの源に繋がっていたから、なのではと思いますいくら人から、信頼されてる人から、言われたとしても、それが自分のパッションの源に乗っかってないと、どんなことがあっても諦めないパワーは生まれないのではないかと思いますそういう意味では、風さんは、もちろん、お父様にパッションの火をつけられたのかもしれないけれども、同時に自らのパッションの源が、音楽にあったからこそ、諦めない気持ちでここまで来られたのかなあと、ひたすら感動してしまいましたそれらの鍵を握る言葉として求められる人になれ、というお父さんの愛に溢れた言葉かなあと思いひとことで言うと求められる人になれノベーションそんなことを思いました^ ^参考: 徹子の部屋 <藤井風>父の教えを胸に・・・「努力」積み重ねた日々 テレビ朝日 9月8日(月)放送 TVerhttps://tver.jp〈藤井風〉父の教えを胸に…「努力」積み重ねた日々動画で見たい方はこちらhttps://youtu.be/9g_p4KtdLSI
13年ぶりの来日のSTOMPに心揺さぶられました!
"バケツ、デッキブラシ、ゴミ箱のふた、そしてビニール袋。日常の身の回りのものから、爆発的に気持ちいいリズムを刻む"
"パーカッション、ダンス、演劇、そして日常の「音」と「動き」が混ざり合う、リズム溢れる衝撃の体感型パフォーマンス!"
"イギリスから旋風を巻き起こし、ニューヨーク・オフ・ブロードウェイで29年のロングラン。世界53カ国で1500万人以上の動員数を誇るショー"
まさに革命的なショーな訳ですが、何故こんなに心揺すぶられるのかを、イノベーター3つのフレームで見てみました
1、パッション
生きる喜び
2、仲間
プリミティブな協調
3、大義
自然への回帰
身の回りにあるものを叩くというのは、もしかすると、もっともプリミティブな音楽の始まりだったんじゃないか
何かやり遂げた時や、わかって欲しい時、思わず周りのものを叩いたり叫んだり、感情の爆発的なものを表現したくなって
そしてそれは、まさに生きる喜びそのもののパッションの爆発なのではないかと
さらにそれが、誰かと協調して行うということに発展して、それが仲間とのコミュニケーションの始まりなんじゃないか
まだ言語がなくても、何かを叩き合って、それでなんらかのコミュニケーションをすることで
最もプリミティブなコミュニケーションが生まれたんじゃないか
そしてそれがどんどん広がっていくことによって、先日の福島さんの音楽の役割のとおり、人間が実は自然の一部だということを思い出させてくれる
そんな素敵な大義が生まれてくるものなんじゃないか
そんなことを、STOMPを見ながら、泣きたくなるほどの感動を味わいながら、血湧き肉踊りながら、思いました
やはりプリミティブなパッションの爆発が、イノベーションとしては、最も強力になるなぁと
そんな話をしています^ ^
参考: STOMP ストンプ シアターオーブ 2023/8/16(水)~8/27(日) たたく!! 鳴らす!! 音と動きが舞うリズム!!
https://theatre-orb.com/s/lineup/23_stomp/
動画で見たい方はこちら
https://youtu.be/YCAZP-Az_5s
山川隆義さんの、"知る知らないマトリクス"に目から鱗が落ちる思いでした
"「横軸に、クライアント(相手の社長)が知っていること、知らないこと。縦軸にクライアント(相手の社長)が知るべきこと、知る必要がないこと。我々は、クライアントが知らなくて、かつ、知るべきことを捻り出すのですよ」"
とても単純ですが、刺さる提案をするために、明快にやるべきことがわかる気がしました
ここから私は、刺さる提案について考えてみました
1、知らないことを徹底的に調べる
→被提案者が触れられない情報
2、知るべきことを徹底的に調べる
→被提案者の真の課題
3、刺さる提案
→得られた示唆
お客様への提案の際に、とかく情報収集も一生懸命やりますが
まずはお客様が触れられない情報はなにか?を一瞬考えることは、刺さる提案にまずは一歩進めるお話かと思いました
また、お客様が知るべきことは何なのか?これはなかなかに難しいお話ですが
これこそ、お客様の真の課題を抉ることになるので、お客様および関連者への何度も対話を重ねていくことかと
この2つを何度も繰り返していくことが、少しずつ刺さる提案に近づいていくことかと思いました
刺さる提案ができないと、よくご相談を受けるのですが、この基本原則を抑えるだけで、ずいぶん変わってくるような気がしました
そんな話をしています^ ^
参考:書籍:瞬考 メカニズムを捉え、仮説を一瞬ではじき出す 発行日 2023年6月5日 第1刷発行 著者 山川隆義 発行所 株式会社かんき出版
動画で見たい方はこちら
https://youtu.be/gQiqhwRpiko
とかく寂しがりな私ですが笑、そんな私に元気を頂けるお話を伺いました
哲学者の岸見一郎さん曰く
"相互依存状態において、各自は自立しているのですが、存在の次元では自分だけで完結しているのではなく、自分が完成するためには他者を必要とし、他者も自分を必要とするので、自分もまた他者を支えなければなりません"
"そこには支配、被支配関係はありません。自分が持てるものが、しかるべき相手の中で共鳴し、自分もまた共鳴します"
"かくて、たとえいつも一緒にいなくても、また、遠く離れていても、互いに影響を及ぼし合うことができるのです"
ここから私は、この状態を作るには?と考えました
1、まずは自分から他者を支える
2、共鳴を感じる
3、課題の分離
イノベーター3つのフレーム、パッション、仲間、大義における、仲間とのあり方だなと
仲間には、家族、恋人、友人、同僚、SNS仲間など、様々な人との関係、全てに当てはまることかと
"相互依存状態"を作ることがポイントになりますが、これも、自分起点、すなわち「パッション」から、他者を支えようとすることから、始まるんだなあと思いました
そして、相互に共鳴を感じてみるということ
さらには、相手の反応などは考えない、つまり考えても分かりようがないことは、気にしない
とかく寂しい時には、誰々が連絡をくれないから!とか、放置プレイなのか?とか、相手に原因を見つけがちですが
どっこい自分起点で支えていこうとしないからであったという衝撃の話かなと思いました
大好きな、ももクロの白金の夜明け、曰く
"誰も1人じゃない、1人になろうとするだけなんだ"
沁みてきます
そんな話をしています^ ^
参考:書籍: 愛とためらいの哲学 著者 岸見一郎 発行所 株式会社PHP研究所 製作日 2022年6月6日
動画で見たい方はこちら
https://youtu.be/GwtNRrHrKJo
「明治おいしい牛乳 」や、NHKの「デザインあ」なども手掛けるグラフィックデザイナーの佐藤卓の言葉に仕事の取り組み方について考えさせられました曰く"自分が何をやりたいかではなくて、やりたいかではなくてやるべきこと。やるべきことを見極めていくっていうこと。でもそれ分かってるんだけど、自我っていうのは出てくるんですよ。自我ってね、どうしても出てきますね。で、それに気がついて、やっぱりそれはここではやるべきではないっていう判断を下さなければいけない。自分に対して、こう厳しくなんなければいけないってことが、まああります。"ここから私は思いました1、自分軸と他人軸のバランス2、イノベーターリップルモデルの中心はペイン3、問題に恋する佐藤さんのデザインされた商品は、どれも若い頃から目にしていたので、驚きと共に感動しました。また、若い頃はアーティストを目指されていたところから、デザイナーへ進むという転身の物語にも感動でした1、自分軸と他人軸のバランスこのお話を聞いてまず思ったのは、自分軸と他人軸のバランスについてです。特にビジネスの世界では、これがとても悩ましいお話としてあると思います自分軸は自らのやりたいこと、他人軸はお客様の実現したいこと、ビジネスマンとしてはこのバランスが微妙に取れていることが、とても大事だと思ってます他人軸によりすぎちゃうと誰に頼んでもいい仕事になるし、自分軸によりすぎちゃうとお客様はどっかに行っちゃう、このバランスを取るのがビジネスマンとして生き生きと仕事ができるかどうかや、成果につながる働き方になると思います佐藤さんのお話は、まさにこの二軸のベン図の真ん中のことをお話しされているのかもしれないなあと思いました想像ですが、佐藤さんはアーティストを目指されていた方なので、特に自分軸としての想いがとても強い方だったのかと思います。それをデザイナーというお客様のご要望をいかに叶えるか、という他人軸もとても大事な役割になり悩まれたのかもしれないと思いましたそれは、決して自分軸を諦めるということではなくて、他人軸からの要望を、自分軸の中で解釈して、お客様でさえ思ってなかった価値を作り出す、そこまで昇華しての上での話だと思いましたこの自分軸と他人軸のバランスをいかに取るか、ここが素晴らしいデザイナーやビジネスマンに大切なことなのだなあと学ばせていただきました2、イノベーターリップルモデルの中心はペイン世の中にこれまでにない新しい価値を生み出す人は、皆、イノベーターと思っているのですが、そのイノベーターに共通してあるフレームを、リップルモデルといつもお話ししていますそれは、自分の内部から出てくる抑えきれない''パッション"を、自分だけではできないことを"仲間"と共に、自分だけが嬉しい価値にとどまらないみんなが喜んでもらえる"大義"として育てていく、というモデルなのですがそのパッションの源を発生させる根源には、誰かの"ペイン''があるという話をしています今回の佐藤さんのお話の中での、やるべきこと、というのは、この"ペイン"を本当に和らげてあげることができるものは何なのか?という問いにも結びつく気がしました他人軸であるお客様のペインを聞いて、自分軸の中でのパッションの源に火をつけて、その上で自分自身のパッションから出てきたやりたいことが、本当にお客様のペインに寄り添えているかをもう一度考えて検証みる、そんなプロセスなのかもしれないなあと思いました3、問題に恋するそれはすなわち、以前もお話しした連続起業家であるユリ・レヴィーンが言われるところの、問題に恋する、ということにつながるのかもしれないなあと思いました他人軸であるお客様のペインを、自分ごとのペインとして捉えられるようなところまで深く理解できれば、それは自らのパッションの源からの抑えられない思いとして、何とか解決したいという、自らのパッションとして、浮かび上がってくるのかもしれないなあと思いましたまた、こちらも以前お話しした、BCGの秘伝のタレの一つ、"他者への貢献に対する強い想い"にも、とても合致してくることかもしれないなあとも思いましたということで、今回の佐藤さんのお話は、デザイナーに限らず、ビジネスマンや誰かのために何らかの価値を作ろうとしている人たちに、とても大切なメッセージとメソッドだなあと思いました一言で言えばやりたいかではなく、やるべきことを見極めるノベーションそんな話をしています^ ^参考:NHK 最後の講義 デザイナー 佐藤卓 1月7日(水)午後10:00 https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-4N7KX1GKN7/ep/MJYK79J5QN
ラストマン・ノベーション(1721回)映画ラストマンにめちゃくちゃ感動したと共に、ラストマンの生き方にイノベーターの考え方を教えて頂きましたプログラムのイントロダクションより"目が見えないからこそ真実を見抜く力を持ち、一人ではなく仲間と助け合いながら難事件に挑む新たなヒーロー像と、今の日本が抱える社会問題にく切り込みながら、誰もが存分に楽しめる珠玉のストーリー。連続ドラマからの魅力はそのままに、映画ならではの圧倒的スケールと、いくつもの謎がちりばめられたサスペンスフルな展開に息をのむ、この冬一番の痛快エンターテインメント作品が誕生!"ここから私は思いました1、頼ることが責任 2、人との違いが価値になる3、違いを前提としたパッションの源を磨く1、頼ることが責任ラストマンがとっても新しいヒーローだなあと思うのは、人に頼ることを前提にしているところです。目が見えないということを、真正面から受け止めて、その上で、できないことはできない人にお願いをするそれは、目が見えないから当たり前ではなくて、自分の生き方としても、自分ができないことを、きちんと人に頼れているか?という問いとなって自分に向かってきた気がしました弱い自己責任のお話を思い出しました。自分が果たすべき責任を自分自身でできないと分かった時点で、堂々と人にこういうことがあるので助けてほしい、と言えるかどうかとかく自分自身で責任を全部引き受けてやっちゃいがちですが、それで責任を果たせない場合が一番よくないと。実は頼ることが、責任を果たすという意味においては、とても大切なことになるケースもたくさんあるそれは頼ることこそが、自分に与えられた責任、ということも、悪いことではなく、むしろ積極的に考える必要があることだと思いました2、人との違いが価値になるラストマンの中で印象的なセリフが、ラストマンのサポートをする大泉洋さんが、"ラストマンは暗闇の中では無敵なんだよ"と言われるシーンがあるのですが、泣けてくると同時に、そういう価値を磨いてきたんだなあということにも感動しましたそれは、ある意味、目が見えないというネガティヴに捉えられることは、人とは違う特徴で、その特徴があるからこその価値があり、それをひたすらに磨いてきた、そういうことなんだなあと思いました僕は歌で悩んでたとこがあって、お前が歌うとオペラみたいと、ずっと言われてきて、それがすごく嫌でした。永ちゃんみたいに歌ってみたり、ブレスを混ぜながら歌ってみたり、いろいろやったんですがやっぱり、自分らしさが一番なんじゃないかと思って、オペラでいいじゃんと思いながら、今でも歌ってます。それがアカペラでコーラスをやるには、ら本当に大変になる理由でもあるのですが笑それがいつしか自分の価値になる、そんなことを信じてやってるので、とても共感することとして受け取れました3、違いを前提としたパッションの源を磨くそういう意味では、一見、自分ではコンプレックスと思ってる成長・脱出パッションが、新しい価値になると信じて、その前提での、自分自身のパッションの源に沿ったものを磨いていくということが、実は他の人とは全然違う個性派パッションに繋がるのかもしれないなあと思いました以前、ダンス振付師のMIKIKOさんのお話を取り上げた際に、"自分しかできないのは何なのかな、そこを100%頑張れてるかな、この体型に生まれたからこそできることって何かな"と言っていたことを思い出しました。自分自身だからこそ、できることって何なのか?という個性派パッションの源をとことんまで突き詰めることで、コンプレックスは、自分の最大の武器になるそんなことを思い出させてもらいましたということで、ラストマンからの学びは弱い責任を果たすために、頼ることを積極的にしていいし、人と違うことはコンプレックスでもあるかもしれないけど、自分唯一の価値にもなりうることで、それをひたすら磨いていくということが、脱出パッションや個性派パッションを育てていく、そんなことになるのかと思いましたラストマンからの学び、一言で言えばラストマン・ノベーションそんな話をしています^_^参考:2025映画「ラストマン」製作委員会 配給 松竹 脚本 黒岩勉 企画プロデュース/東仲恵吾/ 監替/平野俊一 出演/福山雅治 大泉洋/永瀬廉/今田美桜 https://www.lastman2025.jp動画で観たい方はこちらhttps://youtu.be/ogRcbAwLP8o
マイクロソフトAzure Functionsプロダクトチーム シニアソフトウェアエンジニアの牛尾剛さんの、お話しに改めて考えさせられました曰く"長年、私はどうやったら自分の「できない感」から脱却できるか、ずっと解答を探し続けてきた。ソフトウェア業界にいて、同僚たちと比べて自分は頭が悪いと思っていたし、どんなに努力して時間とお金をつぎ込んでも、なかなか「できる」感覚が得られなかった。だが、不全感をつくり出していた根本的な要因は、頭ではなく「思考の習慣」にあった。プログラミングもギターも、「早く成果が欲しくて」、目先の結果を求めて頑張ってはかえってできなくなっていたのだ。どんな人も、最初は難しく、理解には時間がかかるという真実─その本質的な気づきは、最後のワンピースとなって、私が人生で心から欲しかったものを与えてくれた。''ここから私は思いました1、成長曲線2、短期的な成果から長期的な成果へ3、フローへの道のり1、成長曲線英語の練習のように、最初は一向に成果が上がらないけれども、嫌になって辞める寸前に、あ、なんかわかってきたかも、みたいなことになるのが、成長曲線の事例かと思うのですが最初は全然わからない期間が永遠のように続く中で、それを我慢できたものが、ものすごい角度で成長していく段階を迎えて、また最後は緩やかな成長になるという、いわゆるS字カーブというのが米国のスーパーエンジニアの方々にも共通してやっぱりあることなのだということが、とても腑に落ちるお話でした私が思うに成長曲線のようになる理由は、まずは、本質を理解しないと、次のステップに進めないからと思います。イノベーションの作り方でも同じですが、最初にお客様の真の課題を時間をかけて突き止めない限り、おざなりなソリューションになるのと同様に個人の成長のためにも、最初に、本質を理解することに時間をかけることが、実は途中からのレバレッジの角度が急角度になって、誰も追いつけないところまで行ける秘訣なのか、改めて思いました2、短期的な成果から長期的な成果へイノベーションを組織的に大企業で推進してると、すぐに成果を求めてきて、イノベーション活動が止められてしまうと追うこともよくあるかと思いますそれは兎にも角にも、短期的な成果を求めることが原因なのですが、実は組織と同様に個人においても短期的な成果を求めてしまうことで、自分自身の成長曲線を阻害してしまう、ということが行われているなあと、自分自身を振り返っても思いましたそれは忙しさとか、納期とか、あとはKPI達成とか昇進とか、外的要因に支配されてるとも言っていいのかもしれないなと内的要因である、自分の成長やスーパーエンジニアのになりたいなどのパッションの源に従っていれば、実は外的要因に引っ張れなくて済むかもしれない、実はスーパーエンジニアの方々は、そのように育ってきているのかもそれないなあと思いました3、フローへの道のりさらにその先は、成長曲線は最終的にはさちっていくのですが、そこからのさらなる成長は、フローへの道のりに乗っかっていくのかと思いましたフローは、没入体験で凄まじい成果を出す状態ですが、そこへ到達する道のりは、挑戦軸と技術軸のどちらも精緻を遂げること、その先にフローが待っていると思いますつまり、成長曲線で、さちってくるところに、フローにおける挑戦軸が新たに加わることで、新しいS字曲線が生まれ、またレバレッジされていく、そんな繰り返しがさらなる高みへ持っていってくれる秘訣なのかもしれないなと思いましたということで一言で言えばどんな人も、最初は難しく、理解には時間がかかるノベーションそんな話をしています^ ^参考:本: 世界一流エンジニアの思考法 2023年10月20日 発行 著者 牛尾剛 発行所 株式会社文藝春秋
日本からバチカンの教皇選挙にも参加し投票された菊地功枢機卿のアフリカ時代のお話に、心震えました曰く"私がアフリカのガーナという国で働いて 8年間くらい働いてましたけど、それちょうど 1980年代後半から 90年代の頭ですけれどももちろん病気もあるし、貧困もあるし、様々な問題があるにもかかわらずで、私がいったのは山奥の電気も水道もない村でしたけれども、村の人たちがみんなね、明るいんですよ。本当にね笑顔で毎日生活してる、生活は苦しいはずなんですよ。である時その村の人にね、まちょっと冗談めかして、「なんでそんなみんなニコニコしてるの」って話をしたんですよ。そしたら彼らが「いや神父さん神父さん、私たちはね、ガーナのマジック持ってる」と、ガーナマジックって言うんですよね。ガーナマジックってなんだろうと思っていろんな人に聞いたら教えてくれたのは、自分は絶対のたれ死にしないっていう確信で、困ったことがあったら、誰かが助けてくれるっていう確信それがどんなに苦しい状況にあっても、自分は生きていくことができるっていう希望を生み出しているんだって。それがみんなガーナマジックで、みんなだからニコニコして助け合って生きてるんだって。だから互いに助け合って生きていくって、その確信を持ってね、生きていくっていうのはやっぱ、希望を生み出すんだなっていうのはつくづく感じました"ここから私は、イノベーターリップルモデルの周り方を学んだ気がしました1、仲間が希望を生み出す2、希望がパッションに火をつける3、パッションが大義を生み出す1、仲間が希望を生み出すイノベーターリップルモデルは新しい価値を作り出すモデルなので、ある意味、生きがいにもつながるモデルと思ってます今回の話をそれに当てはめると、まずは、仲間との信頼関係が最初にくる重要なお話なんだなあと改めて思いましたセーフティネット的に制度で守る話もありますが、人と人との信頼関係でそれが当たり前にされる世界というのは、なんで素敵なんだろうと思いました人間が社会的な動物だとすれば、それはもしかしたら当然の話なのかもしれないのに、なぜか無関心になってしまうこともある、それこそ、文化的な素養として必要なことなんじゃないかと思いましたある意味、リップルモデルは、自分のパッションから、内発的に始まるという話をいつもしていますが、その前に、まずは仲間との信頼関係から、万が一があっても大丈夫という、心理的安全性が、最初にこともありなのかもしれないなあと思いました2、希望がパッションに火をつけるみんなが助け合って生きていく中で、誰かが、さらによくなる世界を目指して、希望の光を灯す人が出てくるのかもしれないなあと思いましたその人がまさにイノベーターとして、助け合う土壌だからこそ、心理的安全性のもとに、創造性が高まって新たな挑戦を始めてくるそれがイノベーションをその社会に起こす、とても重要な要素なのかもしれないなあと改めて思いました3、パッションが大義を生み出すそして重要なのは、ガーナの皆さんが、大義として、みんながニコニコできる世界でありたい、ということが、あるからこその、ガーナマジックなのかもなあと思いましたそのためには、誰もが挑戦しても、下手こいても、みんなが支え合う土壌があって、そこにいる人たちみんなが仲間として支え合う、そんな文化があるからこそ、ガーナマジックとみんなで言うことができる、素敵な社会だなあと思いました一人一人が弱くても、弱い責任感のように、みんなで助け合うこと大前提の社会的な繋がりをみんなが意識している社会は、素敵だなあと思いましたということで一言で言えばガーナマジックノベーションそんな話をしています参考:NHK こころの時代〜宗教・人生〜2026 宗教の可能性を求めて バチカン「教皇選挙」後の世界 初回放送日 1月4日(日)午前5:00https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-X83KJR6973/ep/W5WLYYVZ3Z
物理学者のアインシュタインからの人はなぜ戦争をするのか?戦争を避けるためにはどうすれば良いのか?への問いへの、心理学者のフロイトの回答に震えました曰く"心理学的な側面から眺めてみた場合、文化が生み出すもっとも顕著な現象は二つです。一つは、知性を強めること。力が増した知性は欲動をコントロールしはじめます。二つ目は、攻撃本能を内に向けること。好都合な面も危険な面も含め、攻撃欲動が内に向かっていくのです。 文化の発展が人間に押しつけたこうした心のあり方─これほど、戦争というものと対立するものはほかにありません。だからこそ、私たちは戦争に憤りを覚え、戦争に我慢がならないのではないでしょうか。""では、すべての人間が平和主義者になるまで、あとどれくらいの時間がかかるのでしょうか?この問いに明確な答えを与えることはできません。けれども、文化の発展が生み出した心のあり方と、将来の戦争がもたらすとてつもない惨禍への不安─この二つのものが近い将来、戦争をなくす方向に人間を動かしていくと期待できるのではないでしょうか。""文化の発展を促せば、戦争の終焉へ向けて歩み出すことができる!"ここから私はイノベーターリップルモデルのフレームで考えてみました1、パッション常に問いを発動させる2、仲間共同体文化活動3、大義文化が戦争を終焉させるメッセージ文化的活動が戦争を終焉させるという、衝撃の内容に驚きと共に、実現するために、イノベーターリップルモデルで、どう変化させていくべきかを考えてみました1、パッション 常に問いを発動させる例えば、芸術や教育やスポーツなどの文化的活動を推進することで、パッションにどんな変化が起こせるのかを考えてみると、「物事に対する問い」を発動できるようになる、ということが一つ大きなこととしてある気がしましたマララさんが、国連総会で演説したことを思い出しました。紛争をなくすためには、本とペン、があればいい、というような内容だったと思いますが自分たちだけで考えていることや風習、ルール、それだけが全てになってしまうと、それ以外のことは悪になり、自分たちだけの正義のもとに、暴力を振るうということも、抑制できなくなってしまうこともあるかとおもいましたその違和感への問いから、新しいパッションの源が生まれることもあれば、自ら信じているパッションの源自身に問いを投げかけて、本当にそれでいいのか?と、本能的なところから一歩引いてメタ認識できるようなことができるようになることも大事かなと思いました2、仲間 共同体文化活動仲間については、自分たちだけが知っている人たちが仲間であるというところから、抜け出すことができるのが、代表的な活動としては、オリンピックやワールドカップのようなスポーツのような共同体としての文化活動が、とても大切なことなのかもしれないなあと思いました私が以前主催をしていた、世界20都市におけるオープンイノベーションコンテストを実施していた時も、各々の国に行けば、食べ物も風習も制度も全て違って当たり前なことがよくわかるし何よりも、どの国の人々も、みんな食べたり飲むことが大好きだし、子供や家族がとても大切だし、誇りを持ってパッションを捧げていることが、それぞれにある、それはどこの国に行ってもおんなじなんだよなあということが、とてもよくわかりましたそういう場に、みんなが集うような、文化的な活動があれば、みんなおんなじなんだということが、肌身でわかるので、とても大切なのかもしれないなあと思いました3、大義 文化が戦争を終焉させるメッセージ今回の話が私の心に刺さったように、実は文化活動が、世界の紛争をなくしていく、大きな一つの手立てであるということを、さまざまな人たちが知ることと、そして、メッセージとして発信していくことが大事と思いました先日のちゃんみなさんの歌のように、大義として、愛と平和のメッセージを出すんだという、どストレートなメッセージを、さまざまな文化的な活動を通じて出していくということが、中長期的な変化をもたらす、そんなことを信じたくなりました最後は、自分たちだけではなく、みんなが素敵に生きていく、そんか世界にしていこう、みんながそれを望んでいるよね、という大きな大義で共感していければ、本当に変わることができる、そんな風に勉強させて頂きましたということで、一言で言えば文化の発展が戦争の終焉に繋がるノベーション(1718回)そんな話をしています参考:本:人はなぜ戦争をするのか? 2016年7月1日 著者 アルバート・アインシュタイン ジグムント・フロイト 訳者 浅見昇吾 発行 講談社
MITスローン経営大学院首席リサーチ・サイエンティストのアンドリュー・マカフィー さんの言葉に痺れました曰く"人類は進化の過程で魅力的な取引をした。集団としてとてつもない力を得た代償として、1人ひとりの無力さを受容したのである。""人間がチンパンジーや他の動物と一線を画す存在になっているのは、「他の人々から学ぶ」からである。""ヒトという種にとって、ホモ・サピエンス(賢い人間)という学名は最適ではないかもしれない。私は、ホモ・ウルトラソーシャリス(超社会的な人間)のほうがふさわしい名前だと思う。私たちを唯一無二の存在にし、繁栄を可能にした要因を強調するのだ。ヒトは他のどんな生き物よりも密接に協力し合い、文化をより速く進化させる。私たちはこの地球で唯一の超社会的な生き物である。""ギーク思考の基本原則は次の通りだ。集団のメンバーの超社会性を方向づけ、集団の文化進化を望ましい方向に可能なかぎり速く進ませる。""ギーク思考はスピード、オーナーシップ、サイエンス、オープンネスで構成される。"ここから私は、 Innovater Ripple Modelから思いました1、"パッション''はあるが1人の無力さの受容2、"仲間"としての超社会性を生む構造設計3、"大義"としての文化進化を望ましい方向性へInnovater Ripple Modelとは、いつも私がお話ししているイノベーターの3つの要素で、うちなる思いの"パッション"に従い、1人ではできないことを"仲間"と共に、1人だけではなくたくさんの人たちが喜んでもらえる"大義"を実現していく、というものですが、このフレームで見てみました1、パッションはあるが1人の無力さの受容1人の無力さを受容するということは、私は自らのパッションを諦めるということではなく、むしろ、自らのパッションはあるけれども、それを実現するためには、1人ではあまりにも無力である、ということを受け入れるということかと思いました以前お話しした、弱い責任感の話を思い出しました。責任感とは決して自分1人で全てを成し遂げるということではなく、もし自分が力不足であれば、それを受容して、むしろ積極的に人を頼る、その上で責任を果たす、ということにとても似ている気がしましたオーナーシップというパッションを持ちながら、無知の知と同様に、無力の知を意識すること、それがとても重要な要素だと思いました2、"仲間"としての超社会性を生む構造設計超社会性を強みとする選択をしたホモ・ウルトラソーシャリスは、"仲間''との関係性を活用してどう強くなっていくのか、進化を遂げていくのかが求められると思いましたその超社会性の構造設計がとても大切になってくると思います。それがいわゆる組織論や、社会構造論などとして発展してきた故、ということも言えるのではないかと思います無力の知を発揮するためには、困った時に頼るということではなく、普段からの信頼関係がとても大切になると思いました。それがオープンネスという言葉にも表れていると思いましたそれは、栗山監督がWBCで言われてていたような、最初にまずは栗山監督が信じているというメッセージを出すことで、大谷翔平さんが大活躍したようにまずは自分から信頼しているメッセージを、オープンに出していくことも大切かもしれないと思いました3、"大義"としての文化進化を望ましい方向性へギーク思考が、文化進化を望ましい方向性へ可能な限り速く進ませる、ということが、最終的に目指すべき"大義"のことだと思いましたさらにそこには、サイエンスとスピードというものを活用しながら大義を目指すというとところが、ギーク思考の特徴的なことかとも思いましたその目指すべき大義は、各々の国や立場によっても全然変わってくる可能性があるからこそ、オーナーシップをとりながらも、オープンネスで、さまざまな軋轢を対話と共に文化進化の望ましい方向性とはなんなのか?それを共に作り出していくことがとても大切なのかもしれないなと思いましたということで、一言で言えばホモ・ウルトラソーシャリス・ノベーションそんなことをお話ししてます参考:本: ギーク思考 圧倒的な結果を出す型破りな思考法 電子書籍データ作成日 2025年10月15日 第1版 著者 アンドリュー・マカフィー 訳 者 小川敏子 発行 株式会社日経BP 日本経済新聞出版
ちゃんみなさんの、REDという曲で伝えたかったことに感動と衝撃を頂きました曰く"私が目指しているゴールって愛と平和なんですよね。そのすごく綺麗事にも聞こえると思うんですけど、私がこのREDで伝えたかったことって。私はこんなに辛かった。私の家族はこんなに辛かった。みんな最低だっていうメッセージじゃないんですよ。私はこんなに辛かったけど。これをちゃんと乗り越えたし、私はそれでも人のことを愛したいっていうメッセージなんですよね。そういう差別的なことを受けた結果が、私は愛をもっと知っていきたいし、みんな愛しているよっていうことだったので。なので、この言葉って締めくくりたかったっていうのは大きいと思います。"ここから私は思いました1、許すことから始めること2、乗り越えて愛すること3、アウフヘーベン1、許すことから始めること衝撃的な差別を受けた経験を歌にしたREDという曲に、込めたメッセージに感動を頂きました怒りのメッセージを叩きつける歌は、たくさんあって、そこからパワーを頂くこともありますが、ちゃんみなさんの曲が素晴らしいのは、その怒りを許すというメッセージが、入ってることかもしれないなあと思いました怒りに怒りでは無限ループに入るのが世の常で、それがなくならないからこそ、さまざまな争いがなくならない原因だと思いますがじゃあ、それを本当に許せるのか?ということは、究極の問いなのだと思います。でもその究極の問いを乗り越えるからこそ、そこに新しい関係性を生むことができるそれは口や頭ではわかるけれども、本当の意味での勇気と覚悟がなければできない、ちゃんみなさんの言われる通り、自分自身がそれを許す、ということで乗り越えるという強い意志がなければできないことで、ちゃんみなさんは、それができるというメッセージをくれている、そんな風に感じました2、乗り越えて愛することまずは相手を許すことができてはじめて、次の段階として相手を愛することに進むような気がしました愛することというのは、心で許すだけではなく、さらにそこから一歩前に進んで、積極的に行動を起こす、ということかもしれないと思いましたちゃんみなさんの凄いところは、それを行動として自らのメッセージとして発信したというところにあるなあと思いましたこころで許すということはできても、それを行動でメッセージで示すということは、今度はそれに対する反発や批判が飛んでくることを覚悟する、という段階に進むということかと思いましたその恐怖を乗り越えて自らが踏み出して全てを自分の責任として受ける覚悟の上で、はじめて愛するという段階に進める、そんなふうにちゃんみなさんをみてて感じました3、アウフヘーベンこの許すからはじめて、そしてお互いに第3の道を探っていこうとする行動、これはすなわち、ヘーゲルさんの言われるアウフヘーベンにも、とても似ていることかもしれないと思いましたお互いを決して否定せずに、また、どちらかが迎合するわけでもなく、お互いの主張を理解した上で、そして許しながら、第3の道をお互いに模索していくそんなことから、差別や格差、さらには対立する関係をなくそうとしていく、そのには、大変な批判や軋轢が伴うから、とても怖い行動だと思いますこれ何も遠い国の紛争の話ではなく、身近な自分たちの周りで常日頃起こっていることで、それを見えないふりをしているだけかもしれないそんな気づきと目を覚ませてくれる、そんなお話に聞こえましたさらに、ちゃんみなさんのこのパッションは、情熱のポートフォリオでいくと、成長・脱出パッションから、愛と平和という大義になり、そこにたくさんの人たちが集まる仲間ができてきている、というイノベーターリップルモデルそのもののような気もしましたということで一言で言えば私はそれでも人のことを愛したいノベーションそんな話をしています^ ^参考: NHK クローズアップ現代 私が社会を変える Z世代を魅了する歌手“ちゃんみな”の闘い2025/12/29(月) https://www.web.nhk/tv/an/gendai/pl/series-tep-R7Y6NGLJ6G/ep/4LRQKL2ZR5
明けましておめでとうございます本年も何卒よろしくお願い致します昨年の本チャネルのベスト50(神3、神7、神40)を独断で選定しました^^全体概要をざっくりお話ししてますので、お年始のお暇な時に、気に入ったものから、または<神3><神7>からお楽しみくださいませ。<神3>1.自分の挑戦は誰かの役に立つノベーション(1370回)https://youtu.be/ZFiQtn9mdMQ2.カメはうさぎに負けないノベーション(1380回)https://youtu.be/B1fbslSRRX03.オリジナリティとは新しい共感であるノベーション(1599回)https://youtu.be/I5l3KpiuyQY <神7>4.自立は薄く広く依存するノベーション(1408回) https://youtu.be/D3wLXUKzh1w5.お前はすでに死んでいるノベーション(1421回)https://youtu.be/nmJgcqf_HFE6.運命の"3デクワス理論"ノベーション(1438回)https://youtu.be/e_l1i46Nd3E7.受信者責任型言語ノベーション(1475回)https://youtu.be/6043guNpWIw8.連続的再学習ノベーション(1485回)https://youtu.be/vA7NB1MSKE8 9.オノマトペ・ノベーション(1503回)https://youtu.be/GFgegsOa3dk10.インターリープ・ノベーション(1672回)https://youtu.be/PC_92wLFygw <神40>11.音楽は人を人たらしめんノベーション(1366回)https://youtu.be/qiu_ph7f2FU12.嫌いの中にこそ強いパッションの源はあるノベーション(1368回)https://youtu.be/3s5Rz49w2Cs13. センスメイキングが変革の種になるノベーション(1383回)https://youtu.be/IerD70dF2q014.熱くサイコパスになるノベーション(1390回)https://youtu.be/mm-zMhqRs2s15.オプション・バリュー・ノベーション(1406回) https://youtu.be/gJVjCYsYuTg16.二兎を追うためにはレンマを探すノベーション(1423回) https://youtu.be/j7Jv17TkH2817."常識変換法"で誰もがイノベーターになれるノベーション(1443回)ttps://youtu.be/tw9NX6l-NHY18.人の"ソース"から世界は前進するノベーション(1463回)https://youtu.be/udgiIb9XQDA19.”問題に恋する”ノベーション(1464回)https://youtu.be/valkghs6MMk20."だって遊んでるんだから"ノベーション(1477回)https://youtu.be/KeVzlcdRWAU21.破壊せず限界を広げるノベーション(1484回)https://youtu.be/o6zj1p49nrY22.概念的×実験的ノベーション(1488回)https://youtu.be/WHg5GQ8fDSw23.そこに大義はあるのかノベーション(1495回)https://youtu.be/gbWDd-hCqAs24.無関心は暴君の支援者となるノベーション(1508回)https://youtu.be/HKvFQPLmLE025.自己修正メカニズム・ノベーション(1522回)https://youtu.be/IhaMPCCH8vI26.「使われなかった人生」を「お使いなさい」ノベーション(1529回)https://youtu.be/pkJGKdwlHuk27.繋がりを知るために生まれてくるノベーション(1534回)https://youtu.be/yQZTkorMdHQ28.はじめに世界観ありきノベーション(1549回)https://youtu.be/1MXfCssYiEs29.寂しくない大人なんていなイノベーション(1550回)https://youtu.be/2TxpnZPeClM30.結晶性知性を伸ばすノベーション(1556回)https://youtu.be/6_-1P-4IET031.本質観取ノベーション(1567回)https://youtu.be/5qgmmdSXLzs32.誰もみてないよノベーション(1572回)https://youtu.be/SBdZmgc5AlI33.組織とは個人の自己実現のための手段であるノベーション(1578回)https://youtu.be/SlJVUOfful834.真の社会課題は人の強欲さノベーション(1584回)https://youtu.be/JjJl2YIpIdk35.蓋然的思考ノベーション(1593回) https://youtu.be/k13yeQdBQtk36.求められる人になれノベーション(1604回)https://youtu.be/9g_p4KtdLSI37.ただ苦ければもっと呑んでやるというくらいの血気ノベーション(1608回)https://youtu.be/7bajPKbB_TI38.何かを生み出すことを心がけなさいノベーション(1607回)https://youtu.be/DazBG0-cIQI39.良い戦略とは、直面する難局から目を逸らさないノベーション(1612回)https://youtu.be/wvu_M684riI40.「いつも心に〝たまたま〟を」のアウト老ノベーション(1622回)https://youtu.be/xt0gX8t6E1o41.自分が最初に感じた疑問をずっと残すノベーション(1624回)https://youtu.be/ecPPVxJwKys42.最下位には最下位のやり方があるノベーション(1627回)https://youtu.be/OMXs3l0BxXo43.アンゾフと渡り廊下ノベーション(1638回)https://youtu.be/dPBZ-P3ETn444.生活の中の小さな挑戦ノベーション(1639回)https://youtu.be/kjtK60ro_dw45.「働き甲斐」改革ノベーション(1645回) https://youtu.be/5j5FhGMQWrs46.結合術 アルス・コンビナトリア・ノベーション(1646回)https://youtu.be/BW4gditSvq847.自分の意思で脱ぐノベーション(1654回)https://youtu.be/YR5vwu79_2g48.私のろうそくは両端から燃えるノベーション(1660回)https://youtu.be/li5YkVJMWMs49.おばけのこノベーション(1671回)https://youtu.be/9H7lmMzC4fc50.ツァイガルニク効果ノベーション(1687回)https://youtu.be/L_t0-Qa3kk4各々の参考先については、リンクの先をご参照くださいませ。もし、私はこの回が好きでしたとかあったら、教えてくださいね。皆様にとって、素敵な年になりますように!!
今日は、我がアカペラグループ香港好運の恒例の年末ワンマンライブでしたが、そこで大きな変化としてAIを駆使して感じたことをまとめてみました1、AIはパッションを拡張する2、圧倒的量とスピードを得られる3、最後に生が勝つ1、AIはパッションを拡張する今回のオープニング映像は、AIでscingoが作り、そして曲は、AIで coyanが作ったものでした。そのAIのオープニング映像が終わって、すぐに我々がアカペラで同じように歌唱して始まる、そんなオープニングでしたここで思ったのは、最初の曲はGloriaというタイトルがついてるのですが、実はcoyanが歌詞などいろんな指示をAIに出して、かつ香港好運のライブという条件も入れて制作していることがとても重要だという点ですつまり、漠然と曲を作っているのでは無く、coyanのパッションがそこにあって、それを表現する方法としてAIが大幅にその思いを拡張して、フルオーケストラのアカペラバージョンが、出来上がったのだなあとかつ、まるで香港好運が歌っているようにも聞こえるために、そこから、繋げて一曲目を始めるというアイデアも手もでてきたわけで、そこにはcoyanの熱き思いを拡張してAIを活用しているということだから、人気投票でも一位を取るくらい人気だったのかなあと、そんなことを思いました2、圧倒的量とスピードを得られる実はcoyanは、他の曲もAIですでに多数作り上げています。一時期は、1日1曲我々のlineに送ってくるほどでしたここから私は思ったのは、AIを活用することで、圧倒的な量とスピードを得られるという点です。実はこの量とスピードは、イノベーションにはとても重要なもので、よく多産多死と言われたり、千三つの世界といわれたりもします有名な画家の方も、実は凡作もたくさんある中で、秀逸な作品が有名になって売れたという話も燃えるよく聞きますつまり、多産多死の状態を作れるAIは、間違いなくイノベーションを加速していくことは間違いないと思いました3、最後に生が勝つKANさんのパクリではないですが、今回AIの歌唱の後に、我々がアナログで歌って重ねた時に当初はアナログの方がしょぼくなりすぎるのではないかと懸念をみんな持っていたのですが、実際にやってみたら、生声の方がめちゃくちゃ音圧と迫力があったということがありましたまた、AIの演奏と歌唱は素晴らしいのですが、やはり家でヘッドホンとかで聞くものだと思いました。つまり、リアルの演奏や歌唱には絶対に届かないということを思いました今回我々は、20年前に作ったプレゼントという曲や、ヒゲダンの日常という曲などをアレンジして、演奏したのですが、相当緊張して各々の顔や息遣いを感じようとして歌っていましたそしてそこにもちろん、未完成なものが加わっていくのですが、その未完成さを6人で必死に最適な解にしていこうともがいている感じが、ある意味ドキュメンタリーのようで面白いのではないかなと思いましたそういう意味で、どんなにAIが優れて出てきても、特にアカペラのような生な世界は、生にこそ更なる価値が生まれる、そんなことを思いましたということで一言で言えばAI香港くんノベーションそんな話をしています^ ^参考: 2025年12月31日○香港好運年末ワンマンライブ「年末恒例の生存確認大会!」 ROCK JOINT GB
ちゃんみなさんの、今持たれている課題感についてのお話に感動し、深く考えさせられました曰く"好きに生きていいよとか、多様性だからって尊重してくれるのはありがたいけども、それってすごく無責任なことで、好きなことを見つけられなかったりとか、するともう悪みたいな風習が、どうしてもあるんじゃないかなと思います。なので、今の子たちは私のファンの子たちの声とかも聞いていて、すごく自分の個性を出すのはすごく怖いけども、かといって個性がないのも怖い好きなことも見つからないけど、好きなことやるのも怖いっていう。その八方塞がりな辛さっていうのは個人的には感じる一つかなと思います。例えばさっきも私のファンの子はダサいって思われないかすごく怖いって、けどじゃあなたにとって一番大切な人は誰なのか?あなただよねってでもあなたが本当に好きでやってんだったら、それでいいし、自分を敬愛する尊敬するって自分が積み上げてきたものを、自分が生きてきた足跡をしっかりと、称えたりとか素晴らしいと認めることって、すごく今の時代こそ大切なものなんじゃないかなとやっぱ自分の娘が生まれて、少しゲップをしただけで周りの人たちが凄いーって言ったりとか、偉いねーってやったりとか、その感覚を自分にも持ってほしい、持ちたいなと思ったんです。自分を可愛がる時間みたいなものは、もっとみんな持ってほしいなと思います。"ここから私は思いました1、自分の足跡を讃える時間を持つ2、自分を可愛がる時間を持つ3、自分のパッションの源を見つめる時間を持つ1、自分の足跡を讃える時間を持つちゃんみなさんの歌は聞いたことがありましたが、肉声をきちんと聴いたことがなかったので、めちゃくちゃ感動しました特に今の課題感に関するこのお話は、いつもパッションの源が大事と言っている私には、かなりガツンとパンチが効いていましたそもそも自分のパッションの源さえも、よくわからなくなってる人たちに、どうしたら良いのかと言う問いを突きつけられた気がして、自分もそんな気持ちになってる時とかもあるなあとも共感しましたまず思ったのは、自らのパッションの源を探る前に、自分自身のこれまでの足跡を改めて見てみて、そしてそれを讃えることをすると言うことがとても大切だと思いましたイノベーションプロジェクトで、まずは、自分の小さい頃やこれまでの歴史を振り返りながら、自分の源を探るセッションなどもやることがあるのですがもっと簡単に、自らを振り返りそしてそれを讃えていく、と言うことをやってみると言うのは、たとえ讃えるようなことがないと思い込んでいても、それでよかったとしたら、何かどんなふうに考えられるかとやってみるのは自らのパッションの癒しでもあり、そこからまた新たな気づきを得ることができるかもしれないと思いました2、自分を可愛がる時間を持つ過去の自分と新たな出会いができたら、今の自分をできるだけ大事にする時間を持つと言うことも、とても大切だと思いました以前、お名前は忘れてしまったのですが、このチャネルでも、一週間に一回は、自分をいわしてくれるそんな時間を持つことが大切とのお話をいただいたことがありました自分は、一種間に一度、20年来の指圧のお店にいくのですが、特に何も話さなくても、私の体に触った瞬間に、今週は寝不足ですねー、とか言われながら、1時間ほとんど寝てますが施術をうけていて、それが週一回のとても自分の癒しになっています他に推し活でも、散歩でも、なんでも良いと思うのですが、自分自身が気持ちいい、と思えて、他のことを何も考えなくてもいい、そんな時間を持つことは、自分をリセットする上でも本当に大切だなあと思いました3、自分のパッションの源を見つめる時間を持つ過去の自分を讃えてあげて、今の自分を可愛がる時間をあげることで、少しずつ自分自身を取り戻せていけるなかの知れないなあと思いましたその上で、自らのパッションの源ってなんだっけ、とか、内側から沸々と込み上げてくるものを待っていても、いいのかなともいましたそもそも好きなものが見つからないだったり、それをやることが怖いってことがあっても、全然いいんだと思います自分自身に前向きに向き会えるようになってから、ゆっくりやっていっていいんだよと、そんなふうに思いましたもしそれが見つかったら、誰に気が削ることなく、自らのパッションの源に真摯に向き合っていけばいいだけ、と思いましたということで、一言で言えば自分を可愛がる時間を持つノベーションそんなことを思いました参考: NHK クローズアップ現代 私が社会を変える Z世代を魅了する歌手“ちゃんみな”の闘い2025/12/29(月) https://www.web.nhk/tv/an/gendai/pl/series-tep-R7Y6NGLJ6G/ep/4LRQKL2ZR5
NHKの大谷翔平さんのインタビューで、「大谷翔平が大谷翔平であり続けるために大切にしていきたいということなんでしょうか」との問いへの答えに震えました曰く''趣味としての野球はやっぱ消したくないなというか、一番根底にある部分だとは思うのでそれはどれだけ上に行っても、やらなきゃいけないことの責任が増えたとしても自分勝手に技術であったりとか、そういうやりたい野球っていうのを求めていく。そういう趣味的な部分を楽しみみたいなという部分はやっぱり持ちたいというか、それは引退するまで持ちたいなとは思っているのでずっとこれまでもやってきましたし、別に変わらなければいいことでもあると思うので。もちろんその他にやらなきゃいけないことはいろいろありますけど。やりたいことはやりたいことでやっていいんじゃないかなと思うので、それは自分勝手に楽しみたいなと思ってます。"ここから私は思いました1、自分軸と他人軸の交わり2、自分軸のみ3、純粋なパッションの源を楽しむこと1、自分軸と他人軸の交わり大谷翔平さんには、本当に今年はたくさん勇気づけられましたので、感謝しかありません。そんな中、この大谷さんの言葉にはとても感動させて頂きましたイノベーションを語る際に、自分軸と他人軸の話をするのですが、自分軸は自分自身が情熱の源に沿って、やりたくて仕方がないことですかたや他人軸は、例えば会社や家族など、自分が所属している組織や集団のことでそこからの要請やそこへの貢献などを求められることを指しています大谷さんの場合は、ドジャースが他人軸に当たると思いますが、今年もチームプレイに全力で貢献する姿をなん度も見て感動だったのですがそれは、他人軸からのある意味要請に、自分軸のパッションを重ねた部分、つまり、ベン図の真ん中をいかにパッションをこめてやるかが求められていたかと思いますが、とても素晴らしい献身的なプレーをされていたなあと改めて思いましたそしてそこの部分はこれからもきっちりやっていくということも意識されているだなあと思いました2、自分軸のみ今回のインタビューでは、趣味としての野球を大切にされたいと言われてだところがまた感動したのですが情熱のポートフォリオでいうと、大好きな野球であり、それによってみんなに喜んでもらう利他パッションであり、二刀流という前人未到の個性派パッションであり、野球がもっと上手くなりたい、技術を磨きたいと追う、あくなき成長パッションでありと情熱のポートフォリオの四象限の全てを、満たして、本当に自らのパッションの源に忠実に向き合って、ある意味、誰からも何を言われてもやるものとして、趣味として、大切にされているんだなあと改めて思いました3、純粋なパッションの源を楽しむことともすると、自分軸としてのパッションの源が、他人軸のプレッシャーに負けて、ベン図の真ん中や、さらに他人軸のみの部分までを、やることにいっぱいいっぱいになってしまって自らのパッションの源さえも苦しくなってきてしまうこともあると思いますが、そこが大谷翔平さんのすごいところであくまでも、自分軸のパッションの源に従うことを第一として、さらには、それを楽しんでいく、というを最も大切にされているということに、感動と共に勉強になりました私も明後日にアカペラグループ香港好運の本番がありますが、新曲を覚えなきゃだし、コールアンドレスポンスのネタはまだだし、などなど、大好きパッションにあるはずなのに、なかなか楽しめていない自分がいて、大谷翔平さんに教えられた気がしましたやっぱり大谷さんの凄さはそこにもあるのかもしれないなあと思いつつということで、一言で言うと自分勝手に楽しみたイノベーションそんなことを思いました^ ^参考: NHKスペシャル 大谷翔平自身が“歴史的死闘”の舞台裏と二刀流復活の真相を語る2025/12/28 https://www.web.nhk/tv/an/special/pl/series-tep-2NY2QQLPM3/ep/B33Y99ZZG3
ダイナミックプライシングで流通にイノベーションを起こしているハルモニアの松村大貴さんから、ブレイクスルーについて教えて頂きました曰く"私たちの当たり前が逆転することです。これまで良かれと思ってきてやっていることの積み重ねが今の社会なんですよね。ちょっとでもいいものを、ちょっとでも次の日に渡していこうっていうことをやってきた結果の今の社会なのでそれによって起きている社会課題っていうのを変えていくには、大きな衝突とか革命とかじゃなくていろんな働きかけによって常識が変わるという、常識が変われば、世の中ちゃんと変わっていくんですね。"ここから私は思いました1、適応からの新たな社会課題2、アジェンダシェイパー3、革命ではなく常識を変える1、適応からの新たな社会課題太刀川さんの進化思考を思い出しました。生きとし生けるものは、その場にどんどん順応していこうとする適応と、変異を起こす中でこれまでの適応における課題を駆逐するものが、新たな適応が始まっていくという適応と変異を繰り返すのが進化思考の本質とすれば、松村さんからのお話は、まさに、これまで適応として当たり前に思われていたことにも、実は新たなる課題が生まれておりそれを解決できる変異を起こすものが、新たな常識として、代替されていく、まさにその生物の、適応と変異の繰り返し的なところに、着目されているのかと思いました2、アジェンダシェイパー山口周さんが教えてくれているアジェンダシェイパーについても思い出しました。世の中の目に見える課題は、すでに多くのものが解決されている物が腐る課題には冷蔵庫、部屋が厚い課題にはエアコンなどなど、だからこそ、これからの世界では、新たな課題を見つける力がとても大事になってくると、アジェンダシェイパーを捉えていますがこれまでの目に見える課題を解決した先に、さらに実は課題が生じてきていて、そこにこそ、新たに解決すべき課題が潜んでいるということかと思いましたそこには、Why not yet、つまり、なぜ今でも解決していないのか?という問いを立て続けることが、とても大切になってくるということが大切だなあと思いました3、革命ではなく常識を変える新たな真の課題が見えてきた時に、それを本当に解決するソリューションを実装させるということにも、とても重要な要素があると思いましたその鍵となるのは時間かと思いました。革命的な行動を起こして一気にひっくり返すということも、やり方として一つあるかとは思いますが、さまざまな軋轢にあって本当の解決策に辿り着かないケースや、またすぐにひっくり返されてしまうというケースも多い気がしますそれは、一時期、Fintechベンチャーがディスラプティブと言われながら金融業界に現れて、時と共に金融機関と融合していったことを思い出しますディスラプティブや革命よりも、そこにある常識をいかに新しい常識に変えていくかという、時間をかけながらの、既存との融合しながらの変革への取り組みこそ、真に新しい常識を作っていく取り組みなのかもしれないなと思いましたということで一言で言えば革命ではなく常識を変えていくノベーションそんなことを思いました^ ^参考: ブレイクスルー 「適正価格」で小売業界を変革!?値付けを自動化するAIシステム テレ東 2025年12月27日(土) file.075 ハルモニア 松村大貴 https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202512/27984_202512271030.html
南極観測隊隊長の原田尚美さんが、何故、南極へ挑戦するモチベーションについて感動しました曰く"そこはですね、まさに南極が持つ魅力なんですよね。私あのいろんな現場やってきて、その北極に行ったり、あるいはチリ沖に行ったり、あの南極以外のフィールドワークもやるんですけれども。南極ほどですね。やっぱり取り憑かれることがないなというか理由を考えると、やっぱり一番難易度高いんですよね。 3回行ってもですね。やっぱり計画した観測のすべてはできていないという現実はあります。ですので、私にとってはですねこの南極、なかなか思い通りにならない恋人のような存在で。一番何もさせてくれないというか、一番思い通りにいかないというか、そこが結果的に何度も何度も挑戦したくなる理由だなと私は理解してます。簡単になんか達成されてしまうようなところは、じゃあもういいかなっていう風に自分の中で区切りをつけやすいんですけど。いや今回もここまでかみたいな感じでですね。やっぱりまたもう 1回行きたいなと、あれもできてないこれもできてないというふうに思うと、また行きたくなってしまうようなですね。"ここから私は思いました1、シーシュポス神話2、フローへの欲求3、成長パッション1、シーシュポス神話永遠に岩を押し上げ続ける男を描いた神話のシーシュポス神話を思い出しました。哲学者のアルベール・カミュは、「山頂に向かう闘争そのものが、人間の心を満たすのだ」と言われたとのこと一見、岩を乗せ続けることは苦行のように見えるけれども、実はその行為自体に意味があるというお話です何らかのゴールに達成することよりも、さらなる高みを目指して挑戦し続ける、その行為自体が、実は心を満たしてくれる、そんな気持ちは自分もわかる気がします達成できないからこそ、何度でも挑戦したくなる、そんな気持ちは、まさにイノベーターマインドセットだなあと思いました2、フローへの欲求チクセントミハイさんのフロー状態への飽くなき挑戦にも思えました。技術軸と挑戦軸の両方が満たされると、没入体験としてフロー状態が訪れるそれは、寝食を忘れるほどの没入体験になるので、さらに挑戦をし続けても苦にならない程に、モチベーションが高まり続けるということもあるのかなあと思いましたイノベーターやアーティストが、終わりなき高みにまで、努力が苦ではなく、むしろ楽しいと思えているみたいなところまで、いく一つの道筋なのかもなあと思いました3、成長パッション情熱のポートフォリオから考えると、飽くなき成長パッションが炸裂している状況とも言えるのかもしれないと思いました情熱は、縦軸にポジティブネガティヴ、横軸にオープンクローズをとると、大好きパッション、利他パッション、個性派パッション、そして成長・脱出パッションに大雑把にわけていますが中でも成長・脱出パッションは、時に物凄く強いパネとなって、イノベーターをとんでも無いところまで引き上げてくれる一つと思っています手に入りそうで手に入らない恋人を手に入れるための、自分自身に課される成長パッションは、例えば、メイクを勉強したり、ダイエット、筋トレ、さらには内面を磨くために、料理教室行ったり、本を読んだり、誰でも経験はあると思いますそのためには、手に入りそうで入らない恋人が、一番必要でわかりやすいなあと思いましたそんな気持ちにさせてくれる、パッションの源琴線に触れる、そんな出会いがとても大切なことだなあと思いましたということで、一言で言えばなかなか思い通りにならない恋人のような存在ノベーションそんなことを思いました^ ^参考: NHKアカデミア原田尚美(後編) 南極観測から見える地球・2025/12/24(水) NHKEテレ東京 https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-XW1RWRY45R/ep/34P568VGQ4動画で観たい方はこちらhttps://youtu.be/0RTA8Gj_xRU